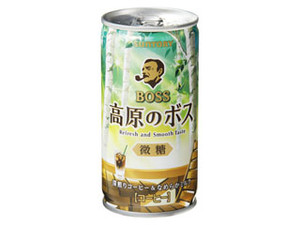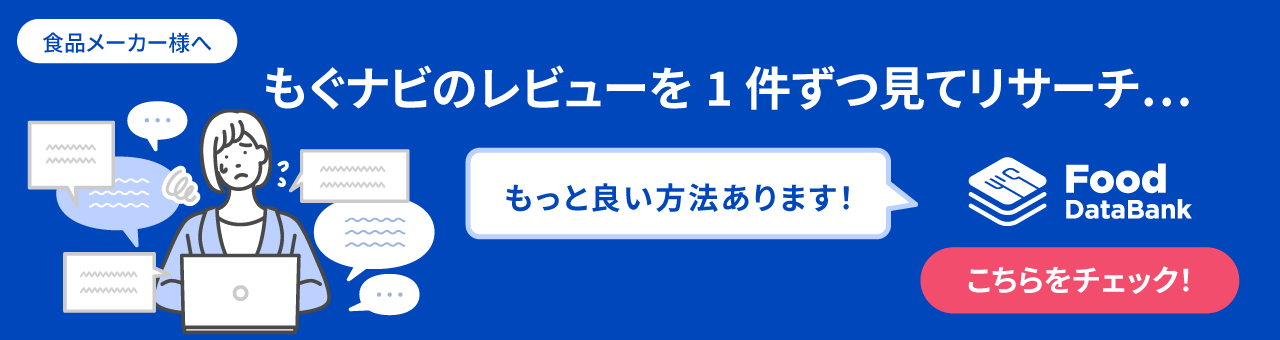普段何気なく飲んでいる「缶コーヒー」。
自動販売機やコンビニの棚に列んでいる「缶コーヒー」には、みなさんが想像する以上におもしろい世界が広がっていました。
今回は、「缶コーヒーレビューブログ 淀橋二郎ドットコム」を運営されている淀橋二郎さんに、知られざる「缶コーヒー」の世界についてお話しを聞いてきました。
缶コーヒーを選んだきっかけ
――缶コーヒーのレビューブログを始めたきっかけを教えてください。
ネット企業に勤めているので、ブログの勉強のために始めたのがきっかけです。
缶コーヒーなら会社で毎日飲んでいるし、安いし、自分でも続けられるだろうという理由だったんですけど、けっこう長く続いちゃってますね。2007年からなので、8年目です。
缶コーヒーレビューブログ 淀橋二郎ドットコム
――ブログを見ると、メジャーな商品から、マイナーな商品まで幅広くレビューをされているようですが、缶コーヒーはどうやって入手しているんですか?
コンビニと自動販売機を中心に、基本的には足で探しています。自分のポリシーとして、通販は使わない。
ただ、やはり自分だけだと限界があるので、会社の人が旅行や出張に行ったときにお願いして買ってもらうことや、人づてにプレゼントしていただくこともあります。
通販を使わないのは、缶コーヒーを入手した地域の特徴や、レアな商品を苦労して入手したエピソードなどもブログに盛り込みたいと思っているからです。
――特に気に入っている地方のメーカーはありますか?
大阪に「DEEN(ディーン)」(西日本ビバレッジ)とういう缶コーヒーがあって、そこで新作が出ると毎回買いに行きます。
あと、福岡にサンコーさんという会社があるんですけど、そこから出している「fabo(ファボ)」という缶コーヒーもおいしいので。
北海道を中心に展開しているコンビニのセイコーマートさんの「GRANDIA(グランディア)」など、その地方に根付いたコンビニやスーパーなどのオリジナル商品も見逃せません。
関西のDEEN、福岡のfabo
――大手メーカーや地方メーカーを含めると、かなりの数になりそうですが、現在発売している缶コーヒーがどのくらいあるか教えてください。
缶コーヒーは、ロング缶やショート缶、ボトル缶などの容器が何種類かあります。
これにスタンダードタイプ(砂糖・ミルク入り)、微糖、糖類ゼロ、カフェオレ、ブラック、デミタスなどのバリエーションをかけ合わせると、一つのメーカーでも最低5種類くらいは出してることになるんですよ。
大手メーカーともなると10種類以上の商品は扱っています。さっき数えてみたんですけど、サントリーさんの「ボス」だけでも20種類以上の缶コーヒーがありました。
経験則ですが、同じ商品のリニューアルも合わせて、大手メーカーだけでも年間100種類以上の新商品が出ていると思います。
清涼飲料業界の中でも、これほど種類が豊富で、新商品が次々に発売されるジャンルはないと思いますし、それが缶コーヒーの面白さでもあるんですよ。
サントリー ボス 高原のボス
――缶コーヒーを探していて、大変だったことやおもしろかったことはありますか?
大変だったのは海外の缶コーヒーを手に入れるときです。
これはもう行くしかない。通販もやってないですし。職場の人や友人が海外に行くときは、買ってきてもらえるように、普段からコミュニケーションを欠かしません(笑)
あとは、旅先で「◯◯という缶コーヒーを探している」とTwitterでつぶやくと、「△△バスターミナルの自販機にある」と返事がきたりすることがあります。
ぼくより詳しい人たちはたくさんいますし、まだまだ知らない缶コーヒーが山ほどあることに驚きます。
海外の缶コーヒーは?
――ディープなコミュニティーができているんですね。さきほど、海外の缶コーヒーのお話しが出ましたが、海外にも缶コーヒーは多いんですか?
海外の缶コーヒーは東南アジア圏が多いです。タイ、ベトナム、マレーシア、台湾、韓国などの缶コーヒーをブログで紹介しています。
逆に、ヨーロッパなどは聞いたことがないんですよ。
もちろん、探せばもしかしたらあるかもしれないんですけど、海外って日本のように自販機がありませんし、カフェの文化が根付いているので、缶コーヒーは飲まれないんでしょうね。
あと、東南アジア圏で普及しているのは、日本のコンビニが進出していたり、気温が高いので甘くて冷たい缶コーヒーが好まれるからかもしれません。
――では、海外の缶コーヒーを見せてもらってもよろしいですか?
これはタイで買ってきた「スズキアイスコーヒー」です。
SUZUKI ICE COFFEE
――確かに「スズキ」って書いてありますね(笑)。
次はこれです。
Red Bull Coffee
なんだこれは?「レッドブル」がコーヒーなのかよと思いました。もったいなくて飲まないでいたら、賞味期限が切れてしまったので、これはコレクションにしています。
国内の珍しい缶コーヒー
あと、国内の珍しい缶コーヒーも。
旭川の「梅屋」という有名なお菓子屋さんが出してるんですよ。
ぼくは札幌のお店まで買いに行ったんですけど、手に入らなくて…。そしたら、缶コーヒーコレクターの方に譲ってもらえました。
菓子処梅屋 オリジナルブレンドコーヒー 微糖
これもすごいですよ。かつて、こんな名前の缶コーヒーがあったのだろうか。
府内南蛮王缶コーヒー 16世紀の大航海時代、九州府内でポルトガル商人たちが嗜んでいた珈琲(南蛮茶)を現在に蘇らせました。また、大吟醸珈琲として缶コーヒー(微糖)として販売されております。
大分のシーアールから出ている「府内南蛮王缶コーヒー」です。キャプションの“大吟醸珈琲”というのもすごいでしょう。こういう掘り出し物がまだまだあるんですよ。
おいしい缶コーヒー
――パッケージのおもしろさも重要ですが、やはり味の話にも触れていきたいと思います。缶コーヒーを飲んでいて、「これはおいしい!」と思うものを教えてください。
最近のお気に入りは、KIRIN「ファイア」です。ファイアは昨年10月にリニューアルして香料無添加になりました。その際に発売された“Wピーク製法”の「ファイア ダブルマウンテン」はなかなか衝撃的な味でした。
また、コーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修の「ジョージア ヨーロピアン」もとてもおいしいですよ。
ジョージア ヨーロピアン プレミアムカフェラテ
おそらく、普段缶コーヒーを飲まれない方にとっては、昔ながらの缶コーヒーのイメージがあるので、「甘くてこんなの全然コーヒーじゃない」と言うと思うんですよ。
スタバやコンビニのコーヒーの方が美味しい、という意見はその通りですが、最近の缶コーヒーは飲んだらビックリするくらい変わってきています。傾向としてはより濃くて、本格的な味が増えてきました。
それに応じて、メーカー側のコーヒー豆、焙煎、挽き方、抽出や香りに至るまでのこだわりもとても強くなっています。
缶コーヒーの変化
――昔と比較して変わったところは他にありますか?
飲料業界全体で言えることだと思うんですけど、数年前から、糖類ゼロとか糖質OFFというジャンルが増えてるじゃないですか。
缶コーヒーでも、砂糖を減らして、アセスルファムカリウムやスクラロースなどの人工甘味料が入った微糖タイプが多くなりました。
一方で、ずっと昔から飲んでいた人たちは「風味が砂糖と違う、後味が好きじゃない」という人も多いです。
コーヒーを飲む楽しみには後味や余韻も含まれているで、飲んでるときは良いんですけど、飲み終わったあとの苦みや香りに人工甘味料の風味が残ると気になってしまいます。
――なるほど。
しかしながら、消費者のニーズとしてはローカロリーや微糖という商品はやっぱり売れます。
昔は砂糖・ミルク入りのロング缶、ショート缶、カフェオレ、無糖ブラックくらいしかなかったのに、そこに微糖、糖類ゼロ、特保などのラインナップも追加されていき、缶コーヒーの種類がどんどん増えてしまいました。
――微糖って甘くないわけではないんですね。
そうなんですよ、微糖というと甘くないイメージですが、人工甘味料は甘いので実際は甘いのです。でも単純に砂糖が少なくて甘くない微糖もあります。ややこしい。
KIRINさんなんて「微糖より、甘くない。」というキャッチの入った商品を出してましたよ(笑)。業界の中でも「微糖」と「甘さ」のルールがハッキリしていないんです。
KIRIN ファイア ダブルマウンテン「微糖より、甘くない。」
これからの缶コーヒーについて
――これから新しい缶コーヒーが出るとしたら、こんなの作って欲しいというイメージはありますか?
いい質問ですね。ただ、最近は特保やエナジー系缶コーヒーなども加わり、すでにも多くの種類の商品が出てるんですよ。
これはぼくの持論なんですけど、「缶コーヒーは缶コーヒーという飲み物」です。
昨今はコンビニコーヒーの台頭で缶コーヒーは苦戦しているなどと言われていますが、私はそもそも缶コーヒーを喫茶店やコンビニのコーヒーと比べる必要もないと思っています。
むしろ、いわゆる昔ながらのスタンダードタイプと言われているミルク感のある甘い缶コーヒーを進化させてほしいです。どんどん微糖勢に追い潰されていく状況を危惧しています。
また、「ダイドーブレンドコーヒー」「UCC ミルクコーヒー」「ポッカコーヒー オリジナル」などの昔から慣れ親しんだ味を経営判断とかで辞めて欲しくないですね。
DyDo ダイドーブレンドコーヒー
淀橋さん、本日はありがとうございました。
身近なようで意外と知らない、缶コーヒーの世界はいかがでしたか?
まだまだディープな世界が広がっていそうなので、もぐナビ編集部では引き続き淀橋さんと協力して、缶コーヒー業界をウォッチしていきたいと思っています。
乞うご期待ください!